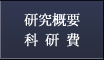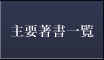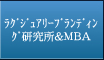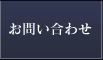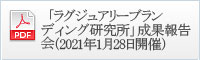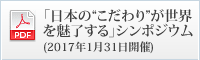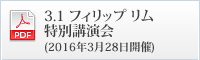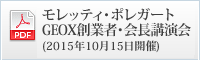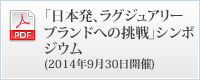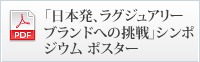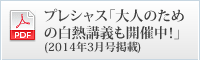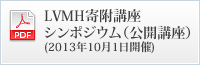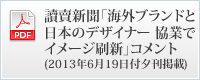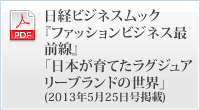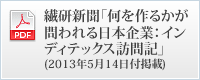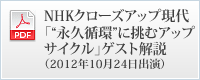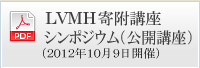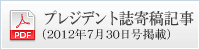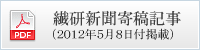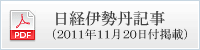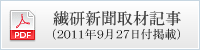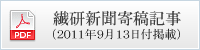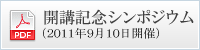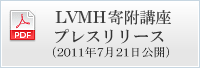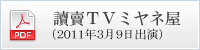![]()
- いわゆるラグジュアリーブランド業界のみならず、富裕層を標的としている業界すべて。例えば自動車、時計・宝飾、香水・化粧品、ファッション等の製造・販売業、豪華クルーズなどの旅行・ホテル業界、百貨店業界等のサービス業も歓迎します。
- 企業経営者、特にブランド価値や顧客価値を高めたい企業経営者およびマネジャー、特にブランドマネジャー、あるいはコンサルタント
- 今後の発展を目指す企業、ベンチャー企業・中小企業・同族企業・地場産業の経営者
- 欧州市場や、中国・インドなどの新興国市場を狙う企業の経営者
- デザイン戦略・ブランド戦略・マーケティング戦略や経営戦略の実務担当者
外国人がゲストスピーカーの場合、英語による講演と質疑応答を実施していますので、ある程度の英語能力が望まれます。
(ご参考)2016年度在学生の年齢、業種
- ♦30代 男(スポーツブランド) 男(欧州ラグジュアリー自動車ブランド) 男(マーケティング・コンサルタント)
- ♦40代 男(アパレル) 女(設計施工) 女(欧州ラグジュアリーブランド) 女(放送)
ブランドビジネスにとって一番大切なこと
- 坂東佑治
- 2016年3月専門職学位課程修了、MBA。日本発テック系スタートアップ企業

ゼミの1年目には、大阪大学大学院のピエール=イヴ・ドンゼ教授の著書をゼミ生全員で分担翻訳し、書籍『「機械式時計」という名のラグジュアリー戦略』、世界文化社ステファニア・サヴィオロファッション&ラグジュアリー企業のマネジメント―ブランド経営をデザインする―』(長沢伸也監修・訳、早稲田大学ビジネススクール長沢研究室(坂東佑・内田留美他)共訳、世界文化社、2014年)として出版する機会をいただいた。他のゼミでは得られない成果となった。
専門職学位論文では、新興ブランドを取り上げた。私自身、実体験として、ブランドビジネスをしてきたにも拘らず、その習慣的な業務がなぜ必要なのかを理論立てて説明できないことがストレスだった。
「あのブランドいいよね」「カッコいいよね」、人々はなぜそう思うのか? なぜブランドのファンになるのか? SNSを代表とするデジタルマーケティングが蔓延し、ブランドビジネスにとって一番大切なことが軽視されている気がしている。もしもあなたが今、ブランドビジネスに携わっていらっしゃるなら、今一度原点に戻り、自分のブランドのあるべき姿を考えてみて頂きたい。
出典:長沢伸也・坂東佑治共著『ハイエンド型破壊的イノベーションの理論と事例検証-リシャール・ミル、トーキョーバイク、ホワイトマウンテニアリング、バルミューダのブランド戦略-』晃洋書房、2019年、あとがき(注:同書は坂東氏の専門職学位論文を加除修正して出版された)
長沢ゼミでの学びの機会と成果物
- 小宮理恵子
- 2014年3月専門職学位課程修了、MBA。不動産情報会社

ゼミの1年目には、伊ボッコーニ大学大学院のステファニア・サヴィオロ教授らの著書をゼミ生全員で分担翻訳し、書籍『ファッション&ラグジュアリー企業のマネジメント―ブランド経営をデザインする―』(長沢伸也・森本美紀共監訳、安達満、井上龍、小宮理恵子他訳、東洋経済新報社、2013年)として出版する機会をいただいた。他のゼミでは得られない成果となった。
また、長沢ゼミでは各ゼミ生が論文執筆のマイルストーンとして学会発表を行っており、私も長沢教授のご指導の下、2013年の商品開発・管理学会第21回全国大会で発表させていただいた。他大学の教授らを前にした発表で非常に緊張したが、優秀発表賞の候補になるなど思いがけず好評を博し、大きな自信となった。学会用原稿の作成にあたっては、ゼミの先輩である博士課程の入澤裕介さんにアドバイスをいただいたところ、分析が深まるとともに見違えるように原稿の完成度が上がり、修士論文への大きな布石となった。
長沢ゼミは学会発表や論文において求められるレベルが高く、指導も厳しめだが、共に学ぶ仲間がいたからこそ目標を達成することができた。二年間の間には体調を崩して入院したり、論文のテーマがなかなか決められずに苦しい思いをした時期もあった。だが、修了後に振り返ってみれば、ゼミでの厳しい指導で自分を追い込むことができたからこそ、最終的に納得できる論文を書くことができたのだと思っている。そしてその結果として、論文がこうして書籍という形で世に出て、皆様の目に触れる機会をいただけたことを大変嬉しく思っている。
出典:長沢伸也・小宮理恵子共著『コミュニティ・デザインによる賃貸住宅のブランディング-人気シェアハウスの経験価値創造-』晃洋書房、2015年、あとがき(注:同書は小宮氏の専門職学位論文を加除修正して出版された)
専門職学位論文の意義
- 西村 修
- 2015年3月専門職学位課程修了、MBA。外資系スポーツウェアブランド

ビジネススクールでは2年にわたり経営の基礎やマーケティングを学ぶことが出来た。しかしながら学んだ経営学やマーケティングだけではスイスの高級時計ブランドを説明できないことも感じていた。
WBSでは専門職学位論文というものが課せられる。ビジネススクールにおける様々なクラスで課せられるレポートや発表に留まらず、自分の研究成果を論文としてまとめあげなければならないのである。この研究に対して特に厳しく問われるのはその論文のオリジナリティであり、それが何を解き明かすのかというプリミティブな問いである。スイスの企業・ブランド視察で、消費者が機械式時計の背景にコモディティ製品とは全く異なる、同質でない精神性を感じ、それが成功要因につながることを立証したい、と考えていたもののそれを形として人に伝えようとする作業には苦労した。
ビジネススクールで習うフレームワークは知っていて当然であり、自らの問いの質が高められているかが重要なのである。そこでは前提に対しても言及しなければならない。普段職場で仕事をしていると前提条件に対して安易に考えたり、暗黙的に流したりしがちだが本質的な問いを考えるためには前提から疑わなければならないのである。本書で設定した問い、主張は初めから確立されていたわけではない。毎週金曜日の終業後のゼミで発表し、教授から繰り広げられる質問や指導を何度も受けて辿り着いたものである。それまでは大量の書籍で学んだ先人の知恵も自らのものに出来ていなかったといえるだろう。今思えば2年目の後期は一定の間隔で設けられた発表の機会と数度に渡って設定された締め切りを乗り切ることで精一杯であった。そこまでして頑張り続けようと思ったのは周囲に同じように苦労している仲間がいたからでもある。
このように専門職学位論文は、今後もビジネスキャリアを積んで行くにあたり、特に問題解決が求められる場面でその本質的なアプローチ方法の訓練を行った点で非常に意義があったと考えることができるし、同時期に切磋琢磨したゼミ生は今後もかけがえのない仲間であり続けるであろう。
出典:長沢伸也・西村修共著『地場産業の高価格ブランド戦略-朝日酒造・スノーピーク・ゼニス・ウブロに見る感性価値創造-』晃洋書房、2015年、あとがき(注:同書は西村氏の専門職学位論文を加除修正して出版された)

写真:長沢教授とゼミ生